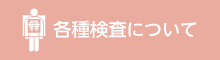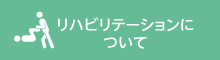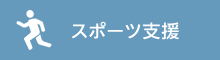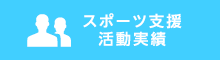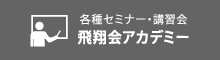トップページ > お知らせ
お知らせ
【蔵本達也のドイツ社会人留学リポート】Vol.31 メンタルの強さと学びの場
スタッフブログ2025/04/22
皆さん、こんにちは。
ドイツもようやく暖かくなり、春の訪れを感じるようになりました。私が暮らすデュッセルドルフでも桜が咲き始め、公園では満開の桜に出会うことができました。思わず足を止めて写真を撮り、日本の春を思い出すひとときとなりました。

今回は、最近心に響いた“ある言葉”から、少しサッカーの話を交えつつ、私自身の経験や学びについて綴ってみたいと思います。
長友佑都選手の言葉に見る、プロの在り方
先日、サッカー日本代表の長友佑都選手のインタビューを耳にする機会がありました。その内容がとても印象的で、今も心に残っています。
インタビューでは、長友選手が森保一監督とのやり取りについて語っていました。試合前夜、ベンチ外となった選手たち一人ひとりに、森保監督は「申し訳ない」と声をかけるそうです。その時、長友選手はこう返したといいます。
「自分は絶対に使わせたいと思わせます。」
今はまだ使えないと思われている。それは自分の実力不足かもしれない。でも、自分は必ずピッチに立つと信じているからこそ、今はチームを冷静に支える。試合に出られない悔しさや、選手たちの焦りも理解している。その中で、彼が伝えるのはこういう言葉です。
「大丈夫だ、俺を見とけ。俺の練習をまず見とけ。」
口先だけではなく、行動で示す。練習からバチバチのモチベーションで挑み、声を出し、全力を尽くす。その姿勢が周囲の選手に影響を与えると、彼は確信しているのです。
この言葉を聞いたとき、長友選手のプロフェッショナルとしての在り方に深く感銘を受けました。そして、日本代表の強さは、こうした選手たちの存在によって支えられているのだと改めて感じました。
思い出した大学時代のエピソード
このインタビューを聞いて、ふと大学時代の出来事を思い出しました。大学3年のとき、DENSOカップという全国大学選抜の大会に、中国・四国地域選抜のメンバーとして出場したときのことです。
この大会には、高校時代に仲の良かった選手も選ばれていました。久しぶりに彼と同じチームで戦えることが嬉しくて、ワクワクしたのを覚えています。しかし、DENSOカップは全員が平等に出場できるわけではなく、試合に1分も出られない選手もいれば、全試合にフル出場する選手もいます。私の友人は、その大会で2日間全く試合に出ることができませんでした。
それでも彼は、不貞腐れることなく、率先してチームの雑用をこなし、試合中もベンチから大きな声を出してチームを鼓舞し続けていました。監督よりも声が出ていたほどです。負けたときも前向きな言葉をかけ、チームが得点を決めたときや勝利したときは、誰よりも大きな声で喜んでいました。
そんな彼にようやく巡ってきたのが、最終試合の残り15分。彼はそのわずかな時間の中でゴールを決め、チームの勝利に貢献しました。
「気持ちには引力がある」
これは私の好きな言葉ですが、まさに彼の行動がそれを証明していたと感じます。試合後、監督やスタッフも彼のメンタリティを高く評価していました。ネガティブな言葉を一切発さず、ポジティブな姿勢でチームを引っ張る姿に、私も心から尊敬の念を抱きました。
彼の行動はまさにそれを体現していたと感じます。周囲を動かす力は、技術や肩書きではなく、心の持ちようから生まれるのだと。
彼は今、山口県の高校で教師をしており、サッカー部の指導にも携わっているそうです。あの時の姿勢を思い返すと、彼が教育者として生徒たちと向き合っている姿は、とても自然なことのように思えます。これからも彼のような人が、日本の若い世代に良い影響を与えてくれると信じています。
フランクフルトでの学び直し──オステオパシーの奥深さ
話は変わりますが、先日、久しぶりにフランクフルトへ行ってきました。目的は、石川先生のもとで開催されたオステオパシーの勉強会に参加するためです。
この勉強会は約1年ぶりの開催。日々の仕事に追われ、なかなか参加できずにいましたが、今回はスケジュールを調整してようやく再び学びの場に立つことができました。
思い返せば、私が石川先生にオステオパシーを教わり始めたのは、「もっと深く身体を理解したい」「本質的なアプローチで人をサポートしたい」と感じたのがきっかけでした。勇気を出して直接メッセージを送り、「どうしても学びたいです」とお願いしたところ、先生は快く受け入れてくださり、それ以来ご指導いただいています。
今回の勉強会では、筋骨格系だけでなく、内臓、神経、そして頭蓋領域まで、多岐にわたる部位へのアプローチを学びました。
・閉鎖口のリリース:骨盤周囲の過緊張を解放し、歩行や立位時の安定性を向上させる。
・骨盤底筋リリース:排泄機能やホルモンバランス、自律神経の調整にも関わる重要なエリア。
・S状結腸・大腰筋・腹部の動き:消化機能や姿勢制御に密接に関わる領域で、腹部の可動性を評価し調整。
・十二指腸のCカーブと肝臓・胃のリリース:内臓由来の不調や腹部の硬さ、消化吸収能力の改善を目的とした繊細な技術。
・仙骨・脊柱の硬さ改善(ムチウチ含む):事故や転倒などで硬くなった脊柱を、呼吸と連動させながら自然な動きを回復させる。
・篩骨・側頭骨・後頭骨のモビライゼーション:頭蓋骨のわずかな動きを感じ取りながら、頭痛や睡眠の質、自律神経の働きを整えるアプローチ。
これらの技術は、いずれも単なるマッサージやストレッチとは一線を画すもので、「触れる」「感じる」「調整する」という繊細な感覚と、深い解剖学的理解が求められます。特に内臓や頭蓋へのアプローチは、表面的には見えにくいものの、身体のバランスや不定愁訴に大きな影響を与えると、改めて感じました。
先生の手技を間近で見て、触れて、実践する中で、知識だけでは補えない「感覚」の部分を養うことの重要性を痛感しました。繰り返し練習を重ねることでしか得られない“手の感覚”というのは、まさに一生をかけて磨いていくものだと思います。
私自身、理学療法士としての基礎に加え、こうした手技療法を学び続けることで、より本質的に、そして根本的に人の身体と向き合えるセラピストになりたいと強く感じています。
オステオパシーの学びには終わりがありません。むしろ学べば学ぶほど、その奥深さに気づかされる毎日です。これからも自分の成長が、クライアントの笑顔やパフォーマンス向上につながるよう、ひとつひとつ丁寧に、そして情熱を持って学び続けていきたいと思います。
日々の現場で結果を出すには、こうした積み重ねがとても重要だと感じています。自分の成長が、関わるクライアントや選手たちのためになる。そう思うと、学びの時間も一層意味のあるものになりますね。
春の訪れとともに、さまざまな「気づき」と「再確認」があった日々でした。これからも、自分自身がプロフェッショナルとしてどうあるべきかを常に問いながら、目の前の人たちに向き合っていきたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



飛翔会の整形外科クリニック